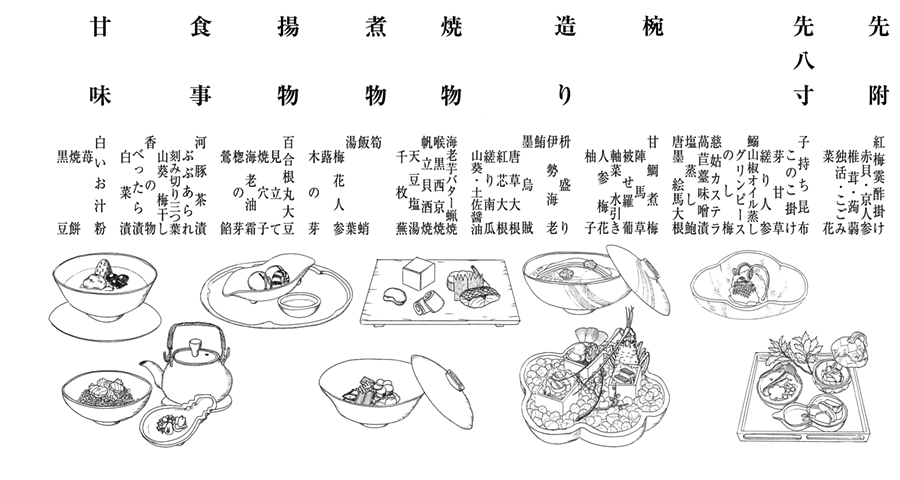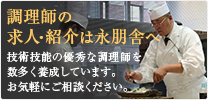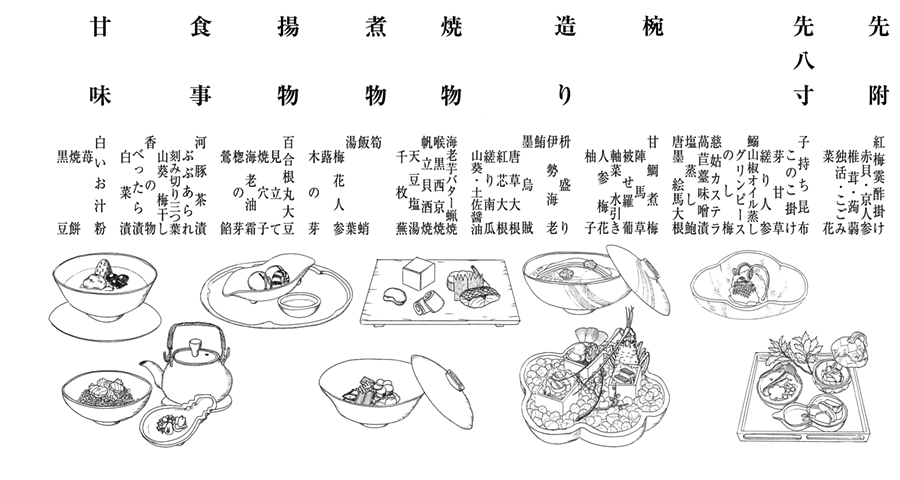
今月の絵献立

- 先附
- 京人参、独活(うど)はそれぞれ短冊に庖丁して塩茹でし、昆布水塩に漬けて置きます。蒟蒻は茹でこぼした後、丘あげし、人参と同様に庖丁します。
- 椎茸は、塩を振り天火で焼き庖丁します。菜花は塩茹でします。それぞれを器に盛り込み、前盛りに鹿の子に庖丁目を入れた赤貝を添え、上からクイジナートで独活と塩ポン酢、赤梅肉を合わせた霙酢を掛け、こごみをあしらい、供します。
- 先八寸
- 子持ち昆布は、適度に塩抜きし、庖丁して器に盛り、このこを掛け、塩茹でした芽甘草と縒り人参をあしらいます。
- 鰯は水洗いした後、塩を当て、粉山椒を入れた米油で2時間程オイル蒸しします。グリンピースは塩茹でした後、蜜に漬けます。のし梅は梅型に抜きます。
- 慈姑(くわい)は皮を剥き20分程度蒸し、裏漉しします。それをクイジナートで慈姑の裏漉し500g、砂糖150g、塩3g、生身50g、黄身3個分、全卵3個を合わせて型に流し、オーブンにて130℃で20分、120℃で20分で焼き上げます。
- 萵苣薹は皮を剥き、塩茹でした後、田舎味噌に1時間位漬けます。
- 鮑は磨いた後、塩を振り30分程なじませ、4時間蒸します。
- 唐墨はさっと炙り、絵馬の形に庖丁した大根を添えます。
- 椀
- 水洗いした甘鯛を酒蒸しします。
- 梅干しをよく水に晒した後、塩が適度に抜けるまで何回か湯を替えながら戻します。それを蒸して水分を飛ばし、吸地で含ませます。陣馬草は塩抜きした後、さっと色出しします。
- 先の物を椀に盛り付け、吸地でさっと炊いた大根を被せ、軸菜、人参、柚子を盛ります。
- 造り
- 枡に伊勢海老洗い、鮪、墨烏賊をそれぞれ盛り付け、あしらいを盛ります。
- 伊勢海老の頭を鬼面に見立てて盛り込み、梅枝を添えます。
- 焼物
- 海老芋は枡型に庖丁し、甘めの出汁で土鍋にて炊き、丘上げし、ガーゼ漉しした卵黄の重量比一割の澄ましバターを入れた物で蝋焼きにします。
- 喉黒は糀味噌と白粒味噌を同量で合わせた味檜床で漬けます。
- 帆立貝は酒を掛けながら、中心は生の状態になるように焼きます。
- 千枚蕪は蕪を厚めにスライスし、強めの塩をした後、適度に塩を抜き、梅酢の効いた甘酢に漬けます。
- 天豆は塩茹でします。
- 煮物
- 筍は糠と鷹の爪で戻します。皮を剥き、庖丁した後、糠の臭みを消すためにさっと茹でて丘あげし、鍋に移し、ひたひたの酒と昆布を入れ火にかけ、沸いたら塩と香り付け程度の淡口醤油を加え、酒がなくなる位まで炊きあげます。
- 飯蛸は下処理をして霜降りし、出汁6、濃口醤油1、砂糖1の合わせ出汁で炊きます。湯葉は吸地の濃い目の味の出汁に甘を入れた地でさっと炊きます。京人参を梅花に剥き、塩茹でし、八方出汁で炊きます。
- 蕗は塩茹でして筋を取り、昆布をさした水塩に地漬けします。
- 揚物
- 百合根は掃除してばらし、20分程蒸して裏漉しします。冷めたら百合根の重量の一割の生身を混ぜ込み、少量の塩で味を入れます。(卵白を少量ずつ加えていき、耳たぶ位の固さにします。)先の百合根を芯に焼穴子を入れて丸に取り、大豆に見立てるため、焼海苔を卵白で付け、きな粉をまぶし余分な粉は刷毛で取り油で揚げます。
- 海老は頭とわたを取り油霜にします。
- たらの芽は掃除して薄衣で天麩羅にします。
- 鶯餅は出汁12、淡口醤油1、味醂1の割合で追い鰹をした地に、純白あたり胡麻を10対1の割合で合わせ、羽二重漉しし、鶯粉を合わせ胡麻地300gに対して15gを溶かします。その他180gに葛粉15gを入れ練ります。
- 食事
- 河豚はしょうさい河豚を使用し、上身にした身を仙台味檜3、田舎味噌1の合わせ味噌に半日程漬け、天火で焼き、粗ほぐしし、椀に御飯を盛った上に盛り付け、ぶぶあられを散らします。味のない一番出汁を火にかけ、沸いたら火を止め煎茶を入れ、炙った河豚ひれの入った急須に漉し入れます。
- 薬味として刻んだ切三つ葉、山葵、ちぎり梅干しを添え供します。
- 甘味
- 白漉しあんを牛乳で延ばし火にかけ、温めます。
- 椀に苺、焼餅、黒豆を盛り付け、先のあんを注ぎます。
二〇二六年
二月の絵献立
一月の絵献立
二〇二五年
十二月の絵献立
十一月の絵献立
十月の絵献立
九月の絵献立
八月の絵献立
七月の絵献立
六月の絵献立
五月の絵献立
四月の絵献立
三月の絵献立
二月の絵献立
一月の絵献立
二〇二四年以前の絵献立は以下からご確認ください。
- 二〇二四年の絵献立
- 二〇二三年の絵献立
- 二〇二二年の絵献立
- 二〇二一年の絵献立
- 二〇二〇年の絵献立
- 二〇一九年の絵献立
- 二〇一八年の絵献立
- 二〇一七年の絵献立
- 二〇一六年の絵献立
- 二〇一五年の絵献立
- 二〇一四年の絵献立
- 二〇一三年の絵献立
- 二〇一二年の絵献立
- 二〇一一年の絵献立