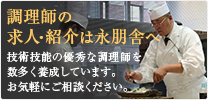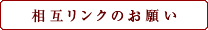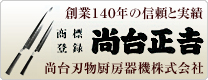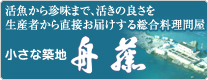令和6年能登半島地震により被災された地域の皆様には謹んでお見舞い申し上げますと共に一日も早い復旧・復興をお祈り致します。
2024年の幕開けは最大震度7を記録した石川県の「能登半島地震」で始まりました。地震と津波、土砂崩れによる甚大な災害で、各県の自治体やボランティア活動の応援を仰ぎながら、道路の修復やがれきの処理、電気、ガス、水道等の復旧作業が続けられています。
三学期を迎える小中学生は親元を離れて、一時的に安全な学校に避難を余儀なくされ、不便を極める避難所には全国から救援物資が届き、寒さを凌ぎながら仮設住宅が設置されるのを待ち望む声が高まっています。災害の絶えない日本では、いつどこで何が起きても不思議ではありませんが、天災は忘れた頃にやってくるという時代ではなくなったようです。
節分は本来、春夏秋冬の移り変わる日の前日をさしていましたが、今では立春の前日のみをさすようになったと言います。また、炒った豆を「福は内、鬼は外」と唱えて福豆をまく習慣も減少し、近年は豆まきよりも関西圈で平成元年頃から始まった。”恵方巻”を食べる習慣が全国的に普及しつつあります。広島県のセブンイレブンで販売されたのが契機となり、その年の恵方(東北東)を向いて7種類の具を巻き込んだ太巻を食べると商売繁盛、無病息災に恵まれるという縁起物です。鬼の金棒に見立てたとの説もあります。
永朋舎の会員のみの新春懇親会は2月18日に行われます。皆さんのご出席をお待ちしております。
編集長 野澤 武