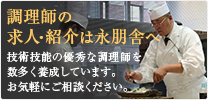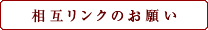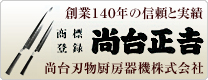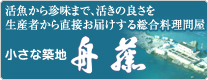今年の9月1日は関東大震災から100年を数えるという。
大正12年(1923年)9月1日午前11時58分(ほぼ正午)に、関東南部を襲った大震災。震源地は相模湾中央でマグニチュード7.9。関東全域と静岡、山梨に地震火災の被害があり、死者・行方不明者10万5千余人といわれています。この関東大震災により、江戸慶長年間に始まった日本橋魚市場(魚河岸)が被災し、千住や芝金杉などの市場を統合して昭和10年(1935年)築地へ移転し、広さ22万平米の東京都中央卸売市場に改組されました。
以来、80年以上にわたり、日本の食文化を支え、プロ・アマ問わず都民の台所としても親しまれてきた築地市場が閉場し、平成30年(2018年)に築地場外市場(築地魚河岸)を残し、新天地豊洲市場に移転して現在に至っています。
近年の大震災と言えば、平成23年(2011年)3月11日に発生した東日本大震災はマグニチュード9.0(世界観測史上4位)の巨大地震と10mを超える大津波に襲われ、福島第一原発が水素爆発し、最も恐ろしい原発事故が起きました。つまりメルトダウンが起きて大量の放射性物質が飛散し、半径20キロ圏内の住民が避難を余儀なくされました。
あれから12年経ち、溜め置いた放射能処理水を、安全性の国際基準を下回る基準で科学的に処理し、環境省の検査のもと、30年以上掛けて海に放出する最終段階に来ているとのことです。
これに対し中国政府は猛反対し、福島産魚介類どころか、日本産や日本製の製品まで輸入差し止めと不買運動を助長させる暴挙に出て、国際世論からも顰蹙(ひんしゅく)を買っています。中国料理の高級食材に不可欠な干し鮑や干し貝柱に用いる日本産の代用はあるのでしょうか。
編集長 日比野隆宏