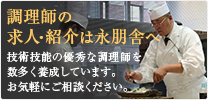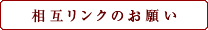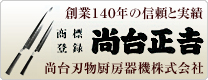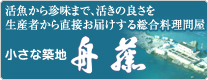残暑お伺い申し上げます
編集部一同
ゲリラ豪雨が各地に洪水や土砂災害をもたらした梅雨が明けると同時に、夏本番の猛暑が日本列島を覆い尽くしています。折しも、コロナ禍による四度目の緊急事態宣言の下、東京では連日千人を超える感染者を出しながら、7月23日から8月8日まで1年遅れの東京2020オリンピックが開幕しました。
新型コロナウイルスがデルタ株等に変異しながら世界中に感染を拡大し、未だに終息の見通しが立たないまま、異常な情況の中、史上初の無観客で実施されることになりました。JOCやIOCの安心安全な五輪のお題目に、感染拡大と重症化を危惧する中止や延期の声も届かず、「復興五輪」のスローガンも今ではコロナに打ち勝つ五輪へとすり替わりました。とにもかくにも206カ国33競技、339種目の大会が東京都を中心に展開されています。
早くも日本人選手の金メダル第1号は柔道ニッポン男子60キロ級の高藤直寿選手が獲得し、翌日には史上初の男子66キロ級の阿部一二三兄と女子52キロ級の妹阿部詩がそろって念願の金メダル、新種目競技のスケボーでは堀米雄斗選手がベストトリックに成功、女子最年少13歳の西矢椛選手と共に金、競泳の大橋悠依が女子400m個人メドレーで日本人初の金、二日日の新種目卓球混合では水谷隼・伊藤美誠組が超難敵中国を撃破し悲願の初優勝。この後も日本人アスリートのメダルラッシュが大いに期待されます。
それにつけても五輪後の一日も早いコロナの終息と日本経済の早期復興が必須であり、会員の皆様には感染と熱中症に留意し、夏を乗り切って欲しいものです。
編集長 日比野隆宏