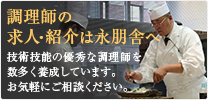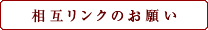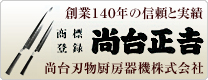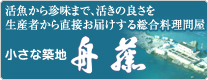去る9月11日、永田町では第四次安倍内閣の顔ぶれが決まったが、2日前に千葉県の南房総を台風15号が襲い、前代未聞の最大瞬間風速57.5mを記録する大災害に見舞われていました。
観測史上最強クラスの台風で、鉄塔や山林の樹木が倒れ、電線を切断したため93万戸が停電、水道とともライフラインを寸断し、数週間にわたり被害地の市民生活を脅かしました。また、農作物や畜産物にも甚大な被害をもたらし、自然災害の恐ろしさを思い知らされました。この度の台風で災害に遭われた地域の皆様にはお見舞いを申し上げますと共に一日も早い復旧をお祈り致します。
スポーツの秋にふさわしく、今年はラグビーの第9回W杯(ワールドカップ2019)日本大会が9月9日より11月2日まで全国各地で開催され、熱戦を繰り広げています。
日本は一次リーグA組ですでにロシア、アイルランドの強豪を破り、8強による決勝トーナメント進出を目指し大健闘中です。プロ野球もセの巨人とパの西武がリーグ優勝を果たし、それぞれCS(クライマックスシリーズ)の第一ステージで勝ち上がったチームと10月9日からの最終ステージを迎えることになります。
いよいよ10月から消費税が8%から10%に増税されます。但し、生活必需品の食料品や新聞は8%の据え置きで、軽減税率制度が低所得者対象を目的として導入されますが、その対象品目となると複雑怪奇で混乱のもとになりそうです。キャッシュレス時代への奨励なのかカード支払いによるポイント還元制などもあり、仕組みがあまりにも複雑過ぎるようです。
編集長 富田正藤