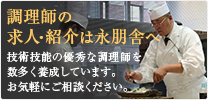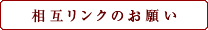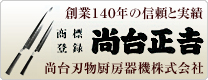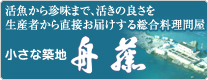東京都中央卸売市場の築地市場から豊洲市場への移転問題も築地再開発の構想を掲げることでようやく決着し、土壌汚染による追加安全対策工事を経て、本年10月11日(木)に開場することになりました。
二年前の都知事選を制した小池百合子知事による豊洲移転延期宣言から三年を費やした膨大な費用の問題も含め、前途多難な船出となりそうです。一方の築地跡地には再開発構想として豊洲と築地を結ぶ食のゾーン「食のテーマパーク」を創設するという提案もあります。
〝銀座から一番近い築地場外〟と称され現在地に残る450店舗からなる築地場外市場は、一昨年オープンした生鮮市場「築地魚河岸」はじめ、新たな未来に向かって世界に名だたる築地の活気と賑わいを取り戻し、本来の「プロの街」としてのプライドを継承すべく、「築地ブランド」の伝統を守っていこうとされています。
築地市場は、江戸時代から続いた日本橋魚河岸が大正12年(1923年)の関東大震災によって壊滅し、昭和10年(1935年)に築地本願寺に隣接する築地海軍技術研究所用地に新たに開設されたのが始まりでした。
歴史は繰り返しますが、永朋舎も二十五周年を迎えます。会員の皆様には最良の年でありますようにお祈り申し上げます。
編集長 富田正藤