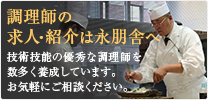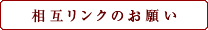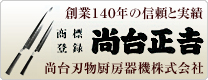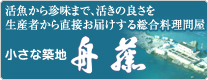献立などに用いられる6月の異名(異称)は水無月が多く、他に歳時記によれば水月、旦月、季月、青水無月、風待月、涼暮月、松風月、鳴神月などがあります。
水無月の語源では梅雨が終わり、水も涸れる意という説と、反対に水の月とする水月は田植えが終わり、田に水をたたえる月であるという説もあります。また一般に青水無月といえば青葉が茂る頃をいい、6月の献立に使う人も多いようです。6月の梅雨時の花には菖蒲(あやめ)や紫陽花などがありますが、梅雨月と同様”菖蒲月”なども和風月名に見当たらないのは意外な感じがします。もっとも菖蒲(しょうぶ)は端午の節句の菖蒲湯に使う葉のイメージがありますから、同じ漢字ですので日本語は紛らわしいものです。
7月になると夏の風物詩の浅草の鬼灯(ほおずき)市や入谷の朝顔市が賑わいを見せます。7月10日の浅草寺(浅草観音)参りは四万六千日にあたり、この日にお参りすれば四万六千日参詣したと同じ功徳があるといわれ、現在でも信仰の対象になっています。京都の清水寺の観音様では二万五千日の功徳があるとされています。
四万六千日の根拠はよくわかりませんが、うがった見方をすると、一年365日で計算してみると126年となり、人生100年時代の究極の生涯年齢を想定させるような数字に思えます。長寿の祝いも白寿までは広辞苑にありますが、百賀の祝いや百寿百福は見当たりません。
余談になりますが、欧州式の結婚式も25年の銀婚式、50年の金婚式までは日本でもよく行われますが、55年のエメラルド婚、60年のダイヤモンド婚は馴染みがありません。それよりも、米国の黄金時代を吹聴するトランプ大統領の相互関税問題は日本経済にとって深刻です。石破政権の命運をかけてぜひとも打開してほしいものです。
編集長 野澤 武