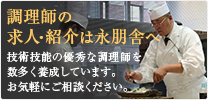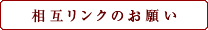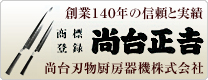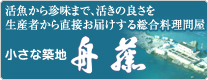終戦から80年目の夏を迎え、終戦記念日に戦没者を追悼し平和を祈念する追悼式での天皇陛下のおことばは印象的でした。
「戦後の長きにわたる平和な歳月に思いを致しつつ、過去を顧み、深い反省の上に立って、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い、戦陣に散り戦禍に倒れた人々に対し、全国民と共に、心から追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。」と結ばれました。
参列した遺族の半数が戦後生まれとなり、戦争を知らない世代が年々増え続けている現状と向き合い、また世界唯一の被爆国として戦争の悲惨さを語り継いでいくことが平和への道筋になることでしょう。
終戦直後の食糧事情は、現代の飽食の時代からは想像も出来ない、食べるもののないまさに耐乏食というものであったと聞いています。昭和21年の東京における統計によると、一日三食を食べているのは会社の重役か医師だけで、サラリーマンは100人の内、12人位で、三食とも雑炊や代用食で凌いでおり、一日中代用食を食べるということは一粒の米も食べられなかったことになります。米を主食にできない当時の上等な代用食はすいとん(メリケン粉=小麦粉を水でこねた団子汁)。それ以下のものには糠団子や菜っ葉汁がありました。
社会問題となった今年の米問題は次年度から生産量を増やすという農水省の方針変更で一段落。もともと日本の主食の米は自給自足出来たのが明治30年頃までといわれ、戦前より朝鮮や台湾から20%も輸入に頼っており、大戦勃発によって輸入が止まり、敗戦による作物の大凶作が相まって、先の米不足による代用食となった過去の経緯を再認識しました。
記録的な猛暑の続く中、実りの秋も近づいてきました。豊かな食材を駆使し、味覚の秋にふさわしい献立作りを楽しみたいものです。
編集長 野澤 武