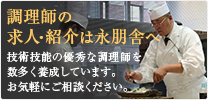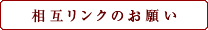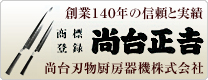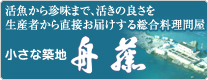みずみずしい稲穂のことを瑞穂といいますが、「瑞穂の国」といえば古来より日本国の美称とされてきました。ほかにも「大和の国」、日出る「日の本の国」などの美称があります。とりわけ「瑞穂の国」に象徴されるように、日本の気候風土に適した「稲作」を中心
に農業が営まれ、米が日本人の主食となってきました。
平成25年(2013)にユネスコの無形文化遺産に登録された「和食」は正しく米飯を中心とした日本食になります。
昨年来、深刻な米不足による価格高騰の話題が絶えない中、江藤拓農水大臣が「私は米を買ったことがありません。支援者の方々がたくさん米を下さり、家の食品庫には売るほどあります」と失言したことで即更迭され、まさに新米の農水大臣に小泉進次郎氏が抜擢
されました。就任するやいなや、政府備蓄米を30万トン放出し、5月に前倒しして5キロ2,000円で大手スーパーと契約し、即時完売になるなど、話題沸騰になりました。早速メディアでは備蓄米を「小泉米」と称し、古古米、古古古米、古古古古米を順次放出することを宣言。コンビニなどでは小分けした1キロ400円の備蓄米も販売されています。
本来、政府備蓄米とは凶作や不作時の流通安定のために、日本国政府が食糧備蓄として保存してある物です。小泉大臣のコメントでは、これからもコメ価格の高騰を安定化させるため、随意契約による備蓄米の放出を決めており、足りなければ輸入することもあるとまで発言し、従来のお米屋さんからは通常価格の米が売れなくなると顰蹙を買っているようです。
梅雨明けの待たれる季節。気候変動によるゲリラ豪雨や異常高温による熱中症警戒アラートには十分に気をつけたいものです。今年の土用丑の日は19日です。鰻を食べて猛暑を乗り切りましょう。
編集長 野澤 武